感情で出産を放棄している引け目
前半では、私が1人しか子供を産んでいないことに関する引け目について書きました。
ざっくりまとめると、「産めよ増やせよ」に逆らって、気分で出産を放棄しているのが申し訳ない感じがしているという話でした。
それも気にしすぎだったのかもしれませんが、10年くらいモヤモヤが続いていました。
そんな中、ハンス・ロスリング著『FACT FULNESS(ファクトフルネス)』を読んで、それがだいぶクリアになってきました。
FACT FULNESS(ファクトフルネス)
『FACT FULNESS(ファクトフルネス)』は、2019年に発行された本です。ハンス・ロスリング、オーラ・ロスリング、アンナ・ロスリング・ロンランドによって著されました。
そこには、私の「引け目」を軽くしてくれたファクトが随所に散りばめられていました。
女性が教育を受けると、良いことが連鎖的に起きる。
職場には多様性が生まれ、意思決定の質も上がり、より多くの問題を解決できるようになる。
教育を受けた母親が増えると子供の数も減り、子供ひとりあたりの教育投資が増える。
女子教育が、社会を変える好循環を生むのだ。
『FACT FULNESS 10の思い込みを乗り越え、データを基に世界を正しく見る習慣』ハンス・ロスリング著
その他にも、世界の進歩と子供の数についての記載がありました。
第3章 直線本能 「世界の人口はひたすら増え続ける」という思い込み
この章で取り上げられているのは、「人口爆発がいつまでも続くわけではない」という話ですが、その中で、女性ひとりあたりの子供の数の平均についても触れられていました。
1800年頃から歴史を通して、女性は平均して5人以上の子供を産んできましたが、1960年代にその数は急激に減少し始め、2017年には2.5人になったそうです。
そしておそらく今後も2人、あるいはそれ以下にまで減少し続けるだろうということでした。
その理由が以下のように記されていました。
これまでの章で紹介してきたように、人類は最近になって多くの進歩を遂げた。それと同じタイミングで、女性ひとりあたりの子供の数も減った。
極度の貧困から抜け出した数十億の人々は、子供をたくさんつくる必要がなくなった。もう、家庭の小さな農園で、たくさんの子供を働かせなくてもいい。もう、病気で亡くなる子供の分だけ、多めに子供をつくらなくていい。
女性も男性も教育を受けるようになると、子供には貧しい思いをさせたくない、もっと良い教育を受けさせたいと考えるようになる。手っ取り早いのは子供の数を減らすことだ。そして、避妊具という文明の利器のおかげで、性交渉の数を減らさずに、子供の数を抑えられるようになった。
これからも、より多くの人が極度の貧困を抜け出し、より多くの女性が教育を受け、性教育や避妊具がどんどん普及していく。女性ひとりあたりの子供の数はこのまま減り続けるだろう。
極度の貧困から抜け出し、教育が行き届けば、自然と子供の数は減っていく。
日本人だけが、私だけが子供を産んでいないのではなく、世界の流れがそうなっている。
過去にもそういう話は聞いたことがあるし、よく考えれば当たり前なことかもしれませんが、これは私にとってかなり勇気づけられるファクトでした。
子供が減るのは世界の進歩
日本でも昔は労働力のために子供を産んでいたというのは聞いた話でしたが、それは当時の日本が「レベル4」の国ではなかったから。
著者は、世界の国々を「先進国」と「発展途上国」と言って分けることはせず、1日あたりの所得によって、「レベル1」~「レベル4」という分け方をしています。
レベルの設定金額等の詳細は他のブログ等に譲りますが、現在最も貧しい「レベル1」の人口は世界の10%で、その女性ひとりあたりの子供の数はおよそ5人。「レベル2」~「レベル4」の子供の数は平均2人とのこと。
しつこいようですが、世界規模で子供の数は減っているのです。
より都合のいい解釈をすると、子供が少ないということは世界が進歩しているということ。
私が子供を1人しか産んでいないのも、世界の進歩が影響しているということ。
これでだいぶ気が楽になりました。
ここで出てくる疑問
ここまで、ファクトフルネスのおかけで私の引け目が軽減されたという話でした。
『ファクトフルネス』を読んで、そしてこの記事を書いてみて改めて、別の考えが頭から離れなくなってしまいました。
そもそも、少子化対策って本当に必要?
これから子供の数が減り続けると分かり切っているならば、お金や労力や時間を使って「産めよ増やせよ」の政策を実行するのに意味があるの?
おそらく何かしらのテコ入れは必要なのでしょうが、力の入れどころが違うような気も。
さらなる勉強が必要ですね。
これはまた別の機会に。
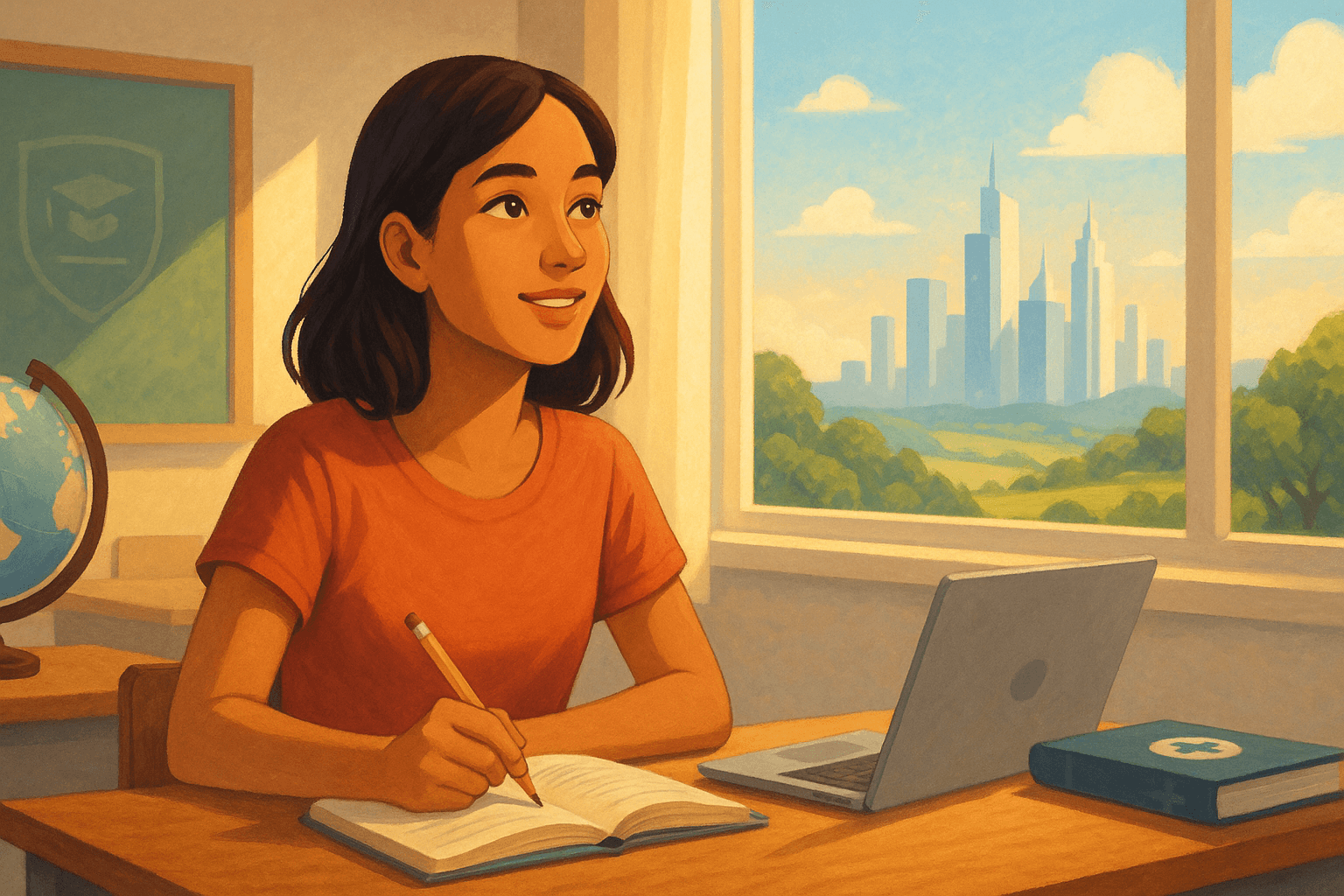


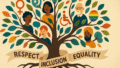
コメント