Facebookが5年前の私の投稿を、「思い出」としてお知らせしてきました。
ちょっと感傷に浸ったので、ここにも残しておこうと思います。
『ダイバーシティという言葉が嫌い。』
ここ数年、多様性だとかダイバーシティだとかいう言葉で何かが語られることが増えましたが、私は自分の職域(リハビリテーション専門職)と養成校で遣われるそれが大嫌いです。
『多様性』にかこつけて、専門職として不適当な人材をなんとか引き上げようとしたり、過剰に保護しようとしたりしているようにしか感じられないから。
もちろん一般的に多様性を認めることは重要で(私も認めていただいてる側の人間ですし)、子育て世代でも独身でも、健康面に不安がある人でも異文化圏の人でも、どんな条件下にあっても生きやすいように、働きやすいように環境や意識を変えていくことは必須だと思っています。
ただね、『多様性を認めるんだ!』と言うあまり、それに引っ張られて周りが害を被ることが非常に増えているように見えるんです。
臨床において知識や技術、コミュニケーションスキルetc.が十分でないがために上手く働けないスタッフに対して、教育の仕方を工夫したり、周りがその人を理解する努力をしたり、時にはぶん殴りたい衝動や自分への飛び火を我慢したりして、なんとかそこそこ動けるように仕立て上げたい、それは当然のみんなの願い。
使えないヤツを放っておいても自然に仕事ができるようになるわけがないし、協調性が高まるわけがないし。それに、そんな人間を置いておくメリットはどこにもないので。
でもその過剰な多様性許容圧力のせいで(誰かがそうさせてるのかどうかは置いといて)、優秀な責任感のある人材が疲弊していって、そいつらが働けなくなったり辞めたりしたらどうなるの?
養成校教育においても、適切なレベルに達していない学生をなんとか引き上げようとするせいで、やれる学生の学ぶ場を奪っていたとしたら?(学校教育には携わっていないので、これ以上は何も言えない。)
よく考えればそんな状況って『ダイバーシティ』でもなんでもないんだけど、なぜかそう捉えている人が多い気がする。
配慮してもらってる側の人間でさえも。
そもそも配慮してもらってると気付かない人や、それが当然だと思っている人さえいる。
「それただのワガママだからね?」と声を大にして言って差し上げたい(言ったことあるけど)。
ただね、やはり今は『多様性を認め合う時代』なんですよ。
ダイバーシティが嫌いとか言っときながら、やっぱりそこからは逃れられない。
教育する側は、なぜ軋轢が生じているのか、どうすれば解決できるのか、そもそも仕事に対する価値観や想いはどんなものなのか、何を大切にして生きているのか等々、相手を理解しようとか認め合おうとか考えなきゃいけない。
優しく伝えるからそれに甘えるんだとか、馴れ合いの環境だから成長しないとか、自分達も厳しく育てられてきたからウンヌンカンヌンとか、上の教育方針がゴニョゴニョとか、視野が狭いね。
そうやって不平不満を垂れ流してる人達って、本当に垂れ流してるだけにしか見えないんだけど、実際のところどうなんでしょうか。
上が決めた方針に納得がいかなかったとき、正面からぶつかって説明を求めたことはあるのかな?
場合によっては反旗を翻したり、泣きながら直談判したことは?
どうにかしてシステムや風土を変えていきたいと願って、起案を出して、何度打ちのめされても練り直して完成させたことは?
なんとかしようとするあまり、出勤できなくなりかけてヤバいと思ったことは?
そうやって行動してきた先輩や後輩がいる(いた)からこそ今があると思っているのだけれど、これから一緒にもっといい未来を『創って』いきたいと願っている私は夢見がちなのでしょうか。
とりあえず文句を垂れ流すだけのヤツは、ギリギリのラインまで1回行ってみろ。
そしたら見える景色がまた違ってくるから。
それでも何も得るものがないのなら、それは『多様性』ってことで、私は受け入れて、それ以上を求めることはやめます。
ちょっと論点はズレるけど、面白いと思うのが、対患者について「全人間的な関わりを!」とか「個別性を!」とか言うくせに、対部下・後輩だと急にそういうこと言わなくなる人がたくさんいるんだけど、それってどういうことなんだろう。
スタッフも人間なんだけど。
いろんなところにケンカを売っている感はありますが、ここ数年の経験による私のひとつの答えです。
ご査収ください。
当時の私、勢いでものを書きがち・・・。
ちょっと恥ずかしいレベル。
確かこれは、臨床家としては尊敬してるけれど管理職としては好きになれなかった先輩が転職したことと、リハビリテーション専門職として最低限のレベルにすら達していない後輩の育成に行き詰ったこと等が重なったタイミングに投稿したものだった気がします。
コメント欄に目をやると、転職した先輩からの発言がありました。
この先輩はKさんとします。
色々、今の、今までの自分の心に刺さる話ですね。
まぁ、俺も多様性って言葉好きじゃない。
もっというとレベルの低い多様性は害が多い。人は集団になると手抜きする可能性が高くなり、周りに合わせたり甘えたりもするしね。
部活とかと学校とかと同じように考えたりすると、偏差値の低い学校で多様性認めたら…なんとなく想像つくと思う。
でも高い学校はお互い争ったり、切磋琢磨するかもしれない。そもそも良い大学に行くとか良い就職先に行くとかの目標がしっかりしている可能性が高い。
また、部活もそう。
弱い部活は弱い理由がある。それは下に合わせたり、統率が取れてない可能性が高いから。強い部活は上に合わせるし弱い人達は淘汰される。
まぁ組織はどっちに振り切ってもリスクがあるから難しいところなんだろうなぁって今は思う。
でも最近テレビで暗殺教室がやってたけど、あれは一つのモデルだなと思う。
出来損ないと思われてたクラスが目標を持つこと、1人の指導者によって変わることとかちょっと勉強になった。
1番大切なのは組織をどうしたいかとクライアントに何を提供したいかの本質と目標設定だと思う。
だから、多様性がどうとか正直どうでもいい気もしてきた。
適材適所と役割分担を組織は明確にして仕事をふるべきだと思うし、やる側は責任を持たなきゃいけない。
でも、○○(私の本名)のいう通り俺はそれを死ぬ気ではしなかった。
背中見せてればいい。背中見せても育たない人間なんて俺はほっとくとここ1年考えちゃってた。今はとても反省してます。
辞めたり長く休んだりすると気付くことって沢山あるんだね。
まぁそうしないと気づけないのもどうかなと思うけど。
今の組織を現場と管理両方見れる、プレイングマネージャーは俺らの世代だったんだから、今この組織はやる気低い人達に合わせすぎてますけど大丈夫ですか?
やる気ある人達はくすぶってますけど僕がどうにかしていいですか?とか、やる気ない人達はそういうのが上手な人に任せますから愚痴は言わないですー!とか。
まさしく、目標設定、目標志向と多様性のある役割分担と責任なのかなって思う。
そして、人は変わらない。
なぜならば現状で既得権益が発生しているから、そして、研鑽しようとしなかろうとある一定のお金をもらえ、苦労しないから。
だから人を変える為にはシステムを変えなきゃいけないとキングコングの西野さんも言っていました。
最近カリスマニートなので人と話さず、まとまりのない文かもですいません。
あっ、あとスタッフも人なんだからには少し反論。
リハビリは不確実性のかたまり、自分はそれなりに研鑽もしてますが、年を重ねれば重ねるほど分からないことが増え、知りたい事が増え、患者さんにやりたい事も増えていきました。
いまだ試行錯誤の毎日、ベストを探し続ける毎日でしたので、正直臨床で疲弊しまくります。
歳とると体力も落ちますしね。でも患者さん相手に手を抜く事、諦める事、失敗を認めない、ベストを求めないなんて出来ないです。
それ踏まえて臨床終わって業務終了後のスタッフ指導に関して、人なんだからとかは理解はしますが正直同意はしかねますね。
教える側も人ですからね。
例えるなら9時から5時までひたすらなんらかの障害を持った子供の育児をし続けて、5時以降に他人の障害は無いのに我がままな子供の面倒を見る気力あります?
みたいな感じです。
だからそれをどうこうするのもシステムかなと。
時間内にやるシステムとかその権限を与えるとか、そして、しっかり結果を出させる。管理者はそれをマネジメントする。
まぁこういう事も死ぬ気でやるべきでしたね。マジ反省!!
ちなみに患者ファーストはダサくても僕は好きですよ。
だからダサいと思われても言い続けます僕は。
これに対する私の返答が、今の私より考えている感じがして驚きました。
私は退化しているのか?
待ってました!
そもそも『多様性』の概念を間違って解釈している人や組織が多いんですよ、日本では。
(このブログは結構分かりやすいです。と書いてリンクを貼っていますが、見られなくなっていました。)
で、正しくない多様性の捉え方のおかげで、私は『ダイバーシティという言葉が嫌い』と言っているのです。
本来の多様性にはレベルの高低なんてないし、足の引っ張り合いなんてないんです。プラスしかない。
だから本文でも『この状況はダイバーシティでもなんでもない』と述べました。
ただ、言葉の定義が日本人は間違ってるだのなんだの言っても状況は変わらないので、現場を何とかするしかないんですよね。
そこで重要なのは、Kさんもおっしゃる通り、目標設定、適材適所、役割分担だと私も考えます。
これがあやふやなせいで、みんな疲れちゃうんですよね。
特に『役割分担』について私は重要視してて。
例えばKさんも私も同じ主任の立場でしたが、スタンスは結構違ったと思うんです。
Kさんは臨床をぶち抜いて頑張りたい人。
私はシステムを変えたい人。
他の主任にもそれぞれの色があります。
それが役割分担であり、かつ多様性であると思います。
だからどの主任像が正解なのかなんてなく、みんなアリなんです(それでも管理職の一員なので、押さえておくべきところはあるとは思いますけどね)。
しかしながら、周り(我々より上の管理職も若手も)がその多様性を受け入れてくれてないという現状もあるかなと。
正直、私も受け入れてなかった時期もあってですね、Kさんにはもっと『管理業務やれよ』と思ってたこともありました。
でもそれじゃつまんないし、発展もないって気付いたんです。
それに私なんかよりももっと早く深く、Kさんの重要性に気付いていて、それを広めたいと願っていた人もたくさんいました。
だから、Kさんには残ってほしかったです、この前LINEでもお伝えしましたが。
Kさんが抜けたことで、リハセンの多様性の一部が欠けてしまいました。
他の管理職にはKさんみたいな人いないので。
同じ県内にいるので、地域を盛り上げるという点では今後もご一緒できますが、もっと近くで罵り合いたかったです。
話が逸れましたね。
目標設定とか適材適所、役割分担が上手くできるようなシステム作りは必要ですよね。
そしてスタッフも人間だって話ですが、もちろん教える側も含めてです。ロボットやらAIやらじゃなく、全員人間です。
だから業務後に後輩に熱心に指導していたKさんを、私は本当に尊敬しています。
学びたいと思う人に、分け隔てなく自分の時間と知識と体力を無償で提供していたわけですから。
あら、また話が逸れた。
戻しますと、だからみんなが少しでも楽になる考え方を追求したいし、システムを作っていきたいと願っているんです(やっぱ私はシステム変えたがり屋さんだ)。
Kさんの返事。
ブログ分かりやすいね!イノベーションの為の多様性なんだね!そりゃプラスしかないわな。また勉強になりました。
お前からはなんだかんだプレッシャーを感じてましたよ…。
でもやっぱりそこは役割分担とイノベーションの為の多様性を認めることが大切なんだろうね!!
確かに今思うともっと罵り合いたかったわ。
まぁ結構時間ない割には絡んでたけどね!大体こっちが突っかかっていった気もするけど…。
そして、業務後の指導をそんな目で見てくれてた人がいたとは…。
ありがとう!!
でもこれからは無償ではやる気は無いですよ。
なぜならば転職で給料下がるので小遣いを稼がなきゃいけないからである!!
でも本当はシステムなんだと今だから思う。
辞めたときに色々な方面の人、いわゆる他職種ね。あるOT、ST、ナースさん、介護士さん、栄養士さんとかに言われたんだけど。Kさんがいなくなったら…ってね。
でもこれって改めて思うと嬉しくないんだよね。
あぁ俺って継続性も無い事を作ってきてしまったんだって。
あとがまも作りきれなかったのかもしれないって。
まぁちゃんと育っている子たちはいるとは思っていたし今も現在進行形で成長してると思うけど。
そう考えたらやっぱり背中見せる事じゃなくてシステム構築が必要だったんだなぁって。
だから○○は間違ってないって思う。
俺は臨床ぶち抜くシステム構築に血反吐吐くぐらいチャレンジしておけば良かったと感じる今日この頃ですわ。
改めて、臨床家として尊敬する先輩だったなと思いました。
先程も書きましたが、当時の私の方が今の私より色々と考えている気がする・・・。
本来の多様性にはレベルの高低なんてないし、足の引っ張り合いなんてないんです。
プラスしかない。
これ、ちょっと忘れかけていました。
重要なことを思い出せて良かった。
そして1点だけ成長したなと思うのが、5年前よりも周りに「噛みつく」ことが減ったこと。
あまり自覚はしていませんでしたが、先日後輩から言われて気付きました。
そしてFacebookのこの投稿を読んで、より実感しました。
少しでも成長したところがあって良かった・・・。
過去の自分やKさんの発言をどう考えるか細かく書いていこうかと思いましたが、今日はここまでにとどめておくことにします。
これはまた別の機会に。
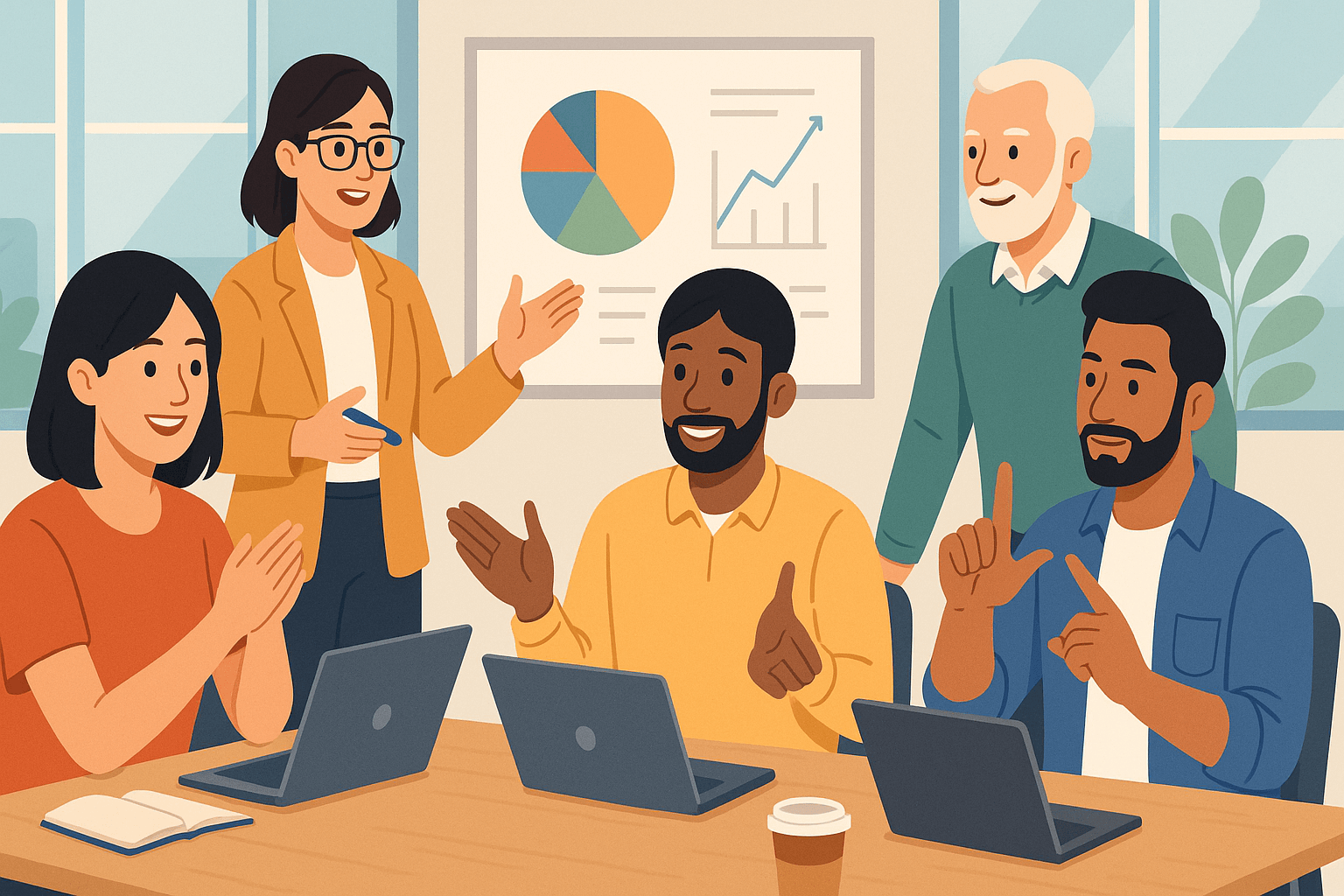


コメント